人─環境
|
|---|
人─機械─人
|
人─機械
|
人─事物─人
|

ネイキッド・ハウゼズ
住環境を仕掛ける:都市の小敷地に建てる
個別に設計した住宅が、この1年ほどの間に次々と竣工した。それぞれ、開発宅地、ミニ開発、町屋といった都市の典型的な小敷地に建てられることになったこれら住宅を通して個別戸建住宅における「住環境」を考えてみたい。
それぞれ開発宅地、ミニ開発、町屋といった、都市の典型的な小敷地に建てられたこれらの住宅は、個別であると同時に集合としての視点も持つことで「住環境」を考えている。都市の居心地を飾りをそぎ落とした裸の住宅で考えてみたい。
ローコストのメリット
三つの住宅とも100㎡くらいの小さなもので、しかもローコストです。
ローコストを売りに設計するつもりはないんだけど、でも結構面白いですよね。
クライアントも安いって意識があると、住宅の快適さや便利さに対して優先順位っていうか自分の希望の全ては無理だろうから、これとこれははずせなくて、こんなとこまでできるとラッキー、っていう意識がはっきりしてませんか。
そういうことは多いかな。またローコストなほど、打合せでそういうことを話していくと、クライアント自身本当に必要なものはなにかって、考えはじめるってこともあります。
設計する側としても、その住宅で実現したいことが鮮明になってくるって言えませんか。
そうそう、ローコストやって自分で自分達の首締めてどうするんだって意見を言われることもあるど、そういう設計してる人たちとぜんぜん違うんだよね視点が。
昔ながらに設計料は工事費の何パーセントですなんて言ってると、そういうことになるかもしれないけど。
そうだよね。それにローコストだからって安い材料使えば済むって訳じゃないしね。
ローコストの設計の場合、単に優先順位っていうだけじゃなくて、どんな「しくみ」をもってくるとどれだけの問題が解けるかっていう検討とそのとき解ける問題の優先順位との組合せで考える必要がある。
ローコストを売りに設計するつもりはないんだけど、でも結構面白いですよね。
クライアントも安いって意識があると、住宅の快適さや便利さに対して優先順位っていうか自分の希望の全ては無理だろうから、これとこれははずせなくて、こんなとこまでできるとラッキー、っていう意識がはっきりしてませんか。
そういうことは多いかな。またローコストなほど、打合せでそういうことを話していくと、クライアント自身本当に必要なものはなにかって、考えはじめるってこともあります。
設計する側としても、その住宅で実現したいことが鮮明になってくるって言えませんか。
そうそう、ローコストやって自分で自分達の首締めてどうするんだって意見を言われることもあるど、そういう設計してる人たちとぜんぜん違うんだよね視点が。
昔ながらに設計料は工事費の何パーセントですなんて言ってると、そういうことになるかもしれないけど。
そうだよね。それにローコストだからって安い材料使えば済むって訳じゃないしね。
ローコストの設計の場合、単に優先順位っていうだけじゃなくて、どんな「しくみ」をもってくるとどれだけの問題が解けるかっていう検討とそのとき解ける問題の優先順位との組合せで考える必要がある。
感覚面積と開放感
ローコストっていうと、面積もきびしいね。
まあ当然ローコストって建てるときだけじゃなく、土地を買うときにもあるんでしょうからね。敷地が狭いとか、建蔽率・容積率が小さいとか。
建物が小さければ必然的に建築費も安くなるし。
そんなとき、何㎡や何坪といった物理面積は同じでも、広い・狭い感じといった感覚面積の違いがありますね。同じ面積でも、少しでも広く感じられるように建てたい。
広い感じって、開放感をどうつくりだすかってとこが重要じゃないですか。
開放感の基本って、両面開放じゃないかな。
両面開放って、北と南とか、西と東とかってことですね。
そう、同時に両方見ることはないんだけど、でもどこか気分が違う。
空間認識って、写真のような1枚の映像として捉えている訳じゃないからね。
人間の感覚って視覚だけじゃないし、視覚情報を受けてるときだって記憶っていうイメージが同時に働いているわけだし、写真って空間のほんの一部しか伝えられないんですよね。
まあそれ以上いうと、じゃなんで雑誌に載せてるんだってことになっちゃうから。
ともかく両面開放は重要だと。
それと開口のもうけかたっていうのも重要かなと思うんです。開けるときは全面あけたい。
そう、特に垂れ壁なんか下がっちゃうとぜんぜんイメージが変わっちゃうよね。
開口を取り囲む床・壁・天井がそのまま開口にぶつかっているっていうのが良いかな。
包み込んでそこに穴を開けるっていうのとは違い、場の覆いかた・囲いかた、そのものを考える。囲ってしまってから穴を開けるんじゃなく、囲わなかった部分が開いているって感じが、開放感には必要ですね。
内部の計画でも、同じようなことが言えませんか。室の配置・配列とか室のつながりかたとかで、住宅内部に開放感を持たせる。
たとえば、室を建具などで区切らず連続的に配列していくとか。
それでは生活できない家族もあるでしょう。
視線が次の室に向かないようにするとか、室を区切る場合でも、行止まりの室にしないとか。とにかく室を連鎖させて必ず一方向だけでなくエスケープできるように配置する。
心理的安心感による解放感ですかね。
まあ当然ローコストって建てるときだけじゃなく、土地を買うときにもあるんでしょうからね。敷地が狭いとか、建蔽率・容積率が小さいとか。
建物が小さければ必然的に建築費も安くなるし。
そんなとき、何㎡や何坪といった物理面積は同じでも、広い・狭い感じといった感覚面積の違いがありますね。同じ面積でも、少しでも広く感じられるように建てたい。
広い感じって、開放感をどうつくりだすかってとこが重要じゃないですか。
開放感の基本って、両面開放じゃないかな。
両面開放って、北と南とか、西と東とかってことですね。
そう、同時に両方見ることはないんだけど、でもどこか気分が違う。
空間認識って、写真のような1枚の映像として捉えている訳じゃないからね。
人間の感覚って視覚だけじゃないし、視覚情報を受けてるときだって記憶っていうイメージが同時に働いているわけだし、写真って空間のほんの一部しか伝えられないんですよね。
まあそれ以上いうと、じゃなんで雑誌に載せてるんだってことになっちゃうから。
ともかく両面開放は重要だと。
それと開口のもうけかたっていうのも重要かなと思うんです。開けるときは全面あけたい。
そう、特に垂れ壁なんか下がっちゃうとぜんぜんイメージが変わっちゃうよね。
開口を取り囲む床・壁・天井がそのまま開口にぶつかっているっていうのが良いかな。
包み込んでそこに穴を開けるっていうのとは違い、場の覆いかた・囲いかた、そのものを考える。囲ってしまってから穴を開けるんじゃなく、囲わなかった部分が開いているって感じが、開放感には必要ですね。
内部の計画でも、同じようなことが言えませんか。室の配置・配列とか室のつながりかたとかで、住宅内部に開放感を持たせる。
たとえば、室を建具などで区切らず連続的に配列していくとか。
それでは生活できない家族もあるでしょう。
視線が次の室に向かないようにするとか、室を区切る場合でも、行止まりの室にしないとか。とにかく室を連鎖させて必ず一方向だけでなくエスケープできるように配置する。
心理的安心感による解放感ですかね。
社会の変化と住環境
住宅の場合、室のつながりかたなんかは、家族のありかたとも関係しますよね。
家族構成の問題じゃなくて家族像っていうか、家族の社会的な存在みたいなもの。家族の形とでもいえば良いかな。
20世紀最後の社会変化は、家族の形にも変化を与えましたよね。家族の形が変わったなら、住環境もそれに対応して変わらないと。
そういうことは今までも言われてまいたよ。nLDKからの脱却とか、フルルームとかいろんな名前も登場したりして。
フルルームでできあがった家は、フルハウス?なんか強そうだね。
そうじゃなくて、nLDKにかわるいろいろなタイプが提案されてきたでしょう。
タイプじゃないんじゃないかなぁ。タイプ化自体が不可能というか、意味をなさなくなったんじゃないでしょうか。
多様化した?
タイプというより新しいしくみっていうかなぁ。
じつはタイプはどうでも良いんじゃないかって。新しいタイプでもnLDKでも、大部屋でも個室でも、何だって住みようによってどうにでもなる。
なんか無責任だなぁ。
タイプを住み手に提示するって、どこか住み手の[住まい力]を見くびっているような感じがするんですよ。
住まい力?
生活力とか、住みこなす能力とか。さらには付け足したり作り変えちゃったりする能力。
住まい力を発揮するためのベースとしての住環境。
住み手の生まい力を信じ、住み手が持っている生まい力に住み手自身が気がつける住環境のしくみってことですか。
住環境と言ったとき、どこか環境工学みたいな自然科学的な環境をイメージしちゃうよね。それだけじゃないんだけど。
社会科学的な環境とか人文科学的な環境とかだね。
住宅がそこに生活する人たちのためやその街区の人たちのために存在するなら、そのために創られる環境は人文科学的な環境も必要なんじゃないか。
また、その住宅やその街区の人たちは、それぞれ社会とつながって社会的な存在でもあるわけだし、その人たちのあいだにも社会が生まれているわけだから、住宅は社会的な意味での環境だ。
家族だって、一人一人にとってみれば社会なんだしね。
そんな住まうことにかかわるさまざまな環境が、住環境って言葉にはあるんだ。で、それを創り出すのが設計者の役割だと。
まさにね。そうなると、設計されるものは建築物にとどまらなくなる。建築って行為と建築物って単純に結びつかなくなってるよね。
建築だけじゃなく、いろいろなものが今までと違う関係になってる。家族なんてのもその代表かな。
家族構成の問題じゃなくて家族像っていうか、家族の社会的な存在みたいなもの。家族の形とでもいえば良いかな。
20世紀最後の社会変化は、家族の形にも変化を与えましたよね。家族の形が変わったなら、住環境もそれに対応して変わらないと。
そういうことは今までも言われてまいたよ。nLDKからの脱却とか、フルルームとかいろんな名前も登場したりして。
フルルームでできあがった家は、フルハウス?なんか強そうだね。
そうじゃなくて、nLDKにかわるいろいろなタイプが提案されてきたでしょう。
タイプじゃないんじゃないかなぁ。タイプ化自体が不可能というか、意味をなさなくなったんじゃないでしょうか。
多様化した?
タイプというより新しいしくみっていうかなぁ。
じつはタイプはどうでも良いんじゃないかって。新しいタイプでもnLDKでも、大部屋でも個室でも、何だって住みようによってどうにでもなる。
なんか無責任だなぁ。
タイプを住み手に提示するって、どこか住み手の[住まい力]を見くびっているような感じがするんですよ。
住まい力?
生活力とか、住みこなす能力とか。さらには付け足したり作り変えちゃったりする能力。
住まい力を発揮するためのベースとしての住環境。
住み手の生まい力を信じ、住み手が持っている生まい力に住み手自身が気がつける住環境のしくみってことですか。
住環境と言ったとき、どこか環境工学みたいな自然科学的な環境をイメージしちゃうよね。それだけじゃないんだけど。
社会科学的な環境とか人文科学的な環境とかだね。
住宅がそこに生活する人たちのためやその街区の人たちのために存在するなら、そのために創られる環境は人文科学的な環境も必要なんじゃないか。
また、その住宅やその街区の人たちは、それぞれ社会とつながって社会的な存在でもあるわけだし、その人たちのあいだにも社会が生まれているわけだから、住宅は社会的な意味での環境だ。
家族だって、一人一人にとってみれば社会なんだしね。
そんな住まうことにかかわるさまざまな環境が、住環境って言葉にはあるんだ。で、それを創り出すのが設計者の役割だと。
まさにね。そうなると、設計されるものは建築物にとどまらなくなる。建築って行為と建築物って単純に結びつかなくなってるよね。
建築だけじゃなく、いろいろなものが今までと違う関係になってる。家族なんてのもその代表かな。
未完成の住宅
家族の形が安定した納まった形をとらなくなった現代でそれを示すのは、住み手に住まい力を想像させる、なにかしくみのようなものが必要なのではないか。
想像喚起力だね。
そう、広い意味での住環境が、住まい手の想像力を喚起できればってことなんだね。
たとえば、安全手摺神話ってあるでしょ。
階段でもヴェランダでも、この高さの手摺付ければ安全だって。で、手摺子の間から落ちてけがすると手摺子間隔はいくつにする、手摺子よじ登ってけがすると手摺子は垂直に。そのたび安全になりましたっていって、結局安全じゃない。
だって階段やヴェランダはそのものが危険な場所だもん。
安全だっていうより、危険だって気が付ける方が良いんじゃないですか。
創り込めば創り込むほど、その場が本来持っている性格が見えなくなっていくようなところがある。
手摺にかぎらず未完であることが想像力を喚起するってことがあるんじゃないかな。
それだけだと無責任だけど、自分の生活環境に自分で手を加えることは当たり前なんだと、住み手が気が付くようにすれば。
暮しながら発見し、住みながら手直ししていく、そういう方向にいくためのしくみが必要だね。
これは都市空間でも同様だと思うけど、住まいや住んでいる街に対してどれだけ愛着が持続されるかが重要だと思う。
自分で考える・作る・直すって、愛着を生むためには有効な行為だよね。
単に使いやすいとか住み易いとか、安全というだけでは愛着は生まれないし、愛着がなければ、メンテナンスもリフォームも始まらないんだ。
そもそも住宅を建てる主体は、住み手にあるはずなんだよ。
設計者ができあがった住宅を、あたかも自分の芸術作品のようにあつかうのは、ちょっと違和感あるよね。
でも建築物っていやでも街並みに現われちゃうから、個人のものだけじゃなく社会的な存在でもあるわけでしょ?
それも含めて、住み手・設計者・施工者がそれぞれの責任と権利のもとに、共同で造るっていう感じかな。
使用者である住み手が、自分達の変化に応じて住環境をアレンジし作り続けていけなきゃ、彼らの責任と権利なんて言えないんじゃないのかな。
住み手がそのことに気がつけるためにも、未完成であることに意味があるんだ。
そして発見し作り直し続ける中で、住環境にたいする愛着を育てる。
住宅を手に入れるって、完成品を商品として買うのとは違うんだよね。それが伝わらないと。
20世紀の社会がそういうしくみで動いていたからね。
変わったんだよ。
社会の今動いているのしくみの中で、これからの有効なしくみを伝えていかなきゃ。
たいへんだな、これは。
いや、おもしろいんだよ、きっと。
想像喚起力だね。
そう、広い意味での住環境が、住まい手の想像力を喚起できればってことなんだね。
たとえば、安全手摺神話ってあるでしょ。
階段でもヴェランダでも、この高さの手摺付ければ安全だって。で、手摺子の間から落ちてけがすると手摺子間隔はいくつにする、手摺子よじ登ってけがすると手摺子は垂直に。そのたび安全になりましたっていって、結局安全じゃない。
だって階段やヴェランダはそのものが危険な場所だもん。
安全だっていうより、危険だって気が付ける方が良いんじゃないですか。
創り込めば創り込むほど、その場が本来持っている性格が見えなくなっていくようなところがある。
手摺にかぎらず未完であることが想像力を喚起するってことがあるんじゃないかな。
それだけだと無責任だけど、自分の生活環境に自分で手を加えることは当たり前なんだと、住み手が気が付くようにすれば。
暮しながら発見し、住みながら手直ししていく、そういう方向にいくためのしくみが必要だね。
これは都市空間でも同様だと思うけど、住まいや住んでいる街に対してどれだけ愛着が持続されるかが重要だと思う。
自分で考える・作る・直すって、愛着を生むためには有効な行為だよね。
単に使いやすいとか住み易いとか、安全というだけでは愛着は生まれないし、愛着がなければ、メンテナンスもリフォームも始まらないんだ。
そもそも住宅を建てる主体は、住み手にあるはずなんだよ。
設計者ができあがった住宅を、あたかも自分の芸術作品のようにあつかうのは、ちょっと違和感あるよね。
でも建築物っていやでも街並みに現われちゃうから、個人のものだけじゃなく社会的な存在でもあるわけでしょ?
それも含めて、住み手・設計者・施工者がそれぞれの責任と権利のもとに、共同で造るっていう感じかな。
使用者である住み手が、自分達の変化に応じて住環境をアレンジし作り続けていけなきゃ、彼らの責任と権利なんて言えないんじゃないのかな。
住み手がそのことに気がつけるためにも、未完成であることに意味があるんだ。
そして発見し作り直し続ける中で、住環境にたいする愛着を育てる。
住宅を手に入れるって、完成品を商品として買うのとは違うんだよね。それが伝わらないと。
20世紀の社会がそういうしくみで動いていたからね。
変わったんだよ。
社会の今動いているのしくみの中で、これからの有効なしくみを伝えていかなきゃ。
たいへんだな、これは。
いや、おもしろいんだよ、きっと。
住環境を考える
そこで、今回のそれぞれの住宅を見ていきたいのですが。
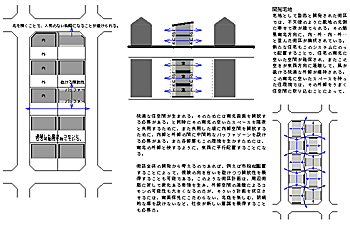 「I-house」の敷地は、中規模開発された、典型的な開発宅地だね。
「I-house」の敷地は、中規模開発された、典型的な開発宅地だね。
プランは、そのまま戸建集合住宅の1住戸みたいですよね。
こんな場所なら、お隣も巻き込んで自発的戸建集合もできるんじゃないの。
可能性はゼロじゃないかもしれないけど、期待してもあんまり意味ないでしょう。
こういう敷地って、みんな敷地の北に寄せて建てているよね。
南面採光と南庭を確保するための計画学だな。
でもいちど敷地境界を無視して眺めてみると、建物の南北に外部を持った配置として見ることもできるよ。
配置はそのままでも悪くないんだ。
すると、南の空きを南隣の家が利用しやすくし、北隣の空きを利用させてもらうための、仕掛けがポイントだ。
それが開放面で内と外をつなぐバッファーゾーンだね。
「SU-HOUSE」は、どちらも旗ざお敷地ですね。
旗ざお敷地って、ミニ開発で分筆されてできる典型的な敷地形状だよね。
ふつう四角の敷地なら、敷地境界のどれか一辺は道路に接しているから、その面は物理的には開放性を持つものだけど。
旗ざお敷地は四方が別の敷地で囲まれてしまい、接道する2mくらいの路地状部分が唯一の開放された場所になる。
とすれば、まずその部分を有効に利用しないとね。
でも、それだけじゃさすがに住環境は厳しいよ。
だから敷地内にもう一箇所オープンスペースをとっているんだ。
すると、旗ざお敷地ではオープンスペースと旗ざお部分との関係で見ることができるね。
その違いによってオープンスペースの性格をアレンジできるんだ。
究極に狭くて、敷地内にオープンスペースが取れないときもあるよね?
そのときはまわりを見て、敷地外のオープンスペースを利用しちゃう。
「八丁堀のローハウス」の敷地は、住宅地じゃないですよね。前面道路も広いし、いわゆる町屋敷地。
都心の事務所・商店・住居の入り混じった場所だよ。
こういう場所は、道路側の開放性は大きいけど、隣地側は住宅地より格段に厳しいね。
隣は7階建てだっけ?
平面的に考えればオープンなのは道路側だけ、でも断面的に考えると屋根の上はずっと空いているんだ。
上空にオープンスペースをとるのか。
都心の込み入った場所では、高層建物じゃない平屋や2階屋でも、環境を立体的にとらえる必要があるんだな。
それに、こういう敷地の高さ制限は一般にゆるいから、建物はある程度高くしておいて部分的に箱抜きすると、隣家がプライバシーを守ってくれる外部スペースも持てる。
この3つの敷地って、住宅が建つ敷地として典型的な3つだよね。この3敷地で都市居住における住環境の仕掛け方のすべてがわかる。
そりゃちょっと言いすぎかな。
でも大まかなところ押えたでしょう。
すでに集合しちゃってる都市では、戸建集合住宅としての設計手法が、戸建でも有効に作用するってことだね。
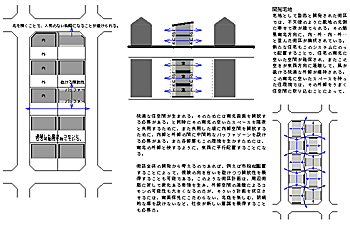 「I-house」の敷地は、中規模開発された、典型的な開発宅地だね。
「I-house」の敷地は、中規模開発された、典型的な開発宅地だね。プランは、そのまま戸建集合住宅の1住戸みたいですよね。
こんな場所なら、お隣も巻き込んで自発的戸建集合もできるんじゃないの。
可能性はゼロじゃないかもしれないけど、期待してもあんまり意味ないでしょう。
こういう敷地って、みんな敷地の北に寄せて建てているよね。
南面採光と南庭を確保するための計画学だな。
でもいちど敷地境界を無視して眺めてみると、建物の南北に外部を持った配置として見ることもできるよ。
配置はそのままでも悪くないんだ。
すると、南の空きを南隣の家が利用しやすくし、北隣の空きを利用させてもらうための、仕掛けがポイントだ。
それが開放面で内と外をつなぐバッファーゾーンだね。
「SU-HOUSE」は、どちらも旗ざお敷地ですね。
旗ざお敷地って、ミニ開発で分筆されてできる典型的な敷地形状だよね。
ふつう四角の敷地なら、敷地境界のどれか一辺は道路に接しているから、その面は物理的には開放性を持つものだけど。
旗ざお敷地は四方が別の敷地で囲まれてしまい、接道する2mくらいの路地状部分が唯一の開放された場所になる。
とすれば、まずその部分を有効に利用しないとね。
でも、それだけじゃさすがに住環境は厳しいよ。
だから敷地内にもう一箇所オープンスペースをとっているんだ。
すると、旗ざお敷地ではオープンスペースと旗ざお部分との関係で見ることができるね。
その違いによってオープンスペースの性格をアレンジできるんだ。
究極に狭くて、敷地内にオープンスペースが取れないときもあるよね?
そのときはまわりを見て、敷地外のオープンスペースを利用しちゃう。
「八丁堀のローハウス」の敷地は、住宅地じゃないですよね。前面道路も広いし、いわゆる町屋敷地。
都心の事務所・商店・住居の入り混じった場所だよ。
こういう場所は、道路側の開放性は大きいけど、隣地側は住宅地より格段に厳しいね。
隣は7階建てだっけ?
平面的に考えればオープンなのは道路側だけ、でも断面的に考えると屋根の上はずっと空いているんだ。
上空にオープンスペースをとるのか。
都心の込み入った場所では、高層建物じゃない平屋や2階屋でも、環境を立体的にとらえる必要があるんだな。
それに、こういう敷地の高さ制限は一般にゆるいから、建物はある程度高くしておいて部分的に箱抜きすると、隣家がプライバシーを守ってくれる外部スペースも持てる。
この3つの敷地って、住宅が建つ敷地として典型的な3つだよね。この3敷地で都市居住における住環境の仕掛け方のすべてがわかる。
そりゃちょっと言いすぎかな。
でも大まかなところ押えたでしょう。
すでに集合しちゃってる都市では、戸建集合住宅としての設計手法が、戸建でも有効に作用するってことだね。
20021001 SpaceLAB.
Copyright©2002-2003 SpaceLAB.co.,ltd.
ご意見・ご感想・ご質問は、spacelab@tokyo.nifty.jp へ
Sorry, Japanese page only.
ご意見・ご感想・ご質問は、spacelab@tokyo.nifty.jp へ
Sorry, Japanese page only.